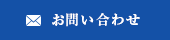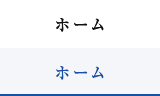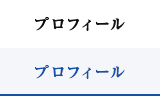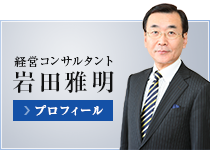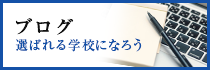教育学術新聞に寄稿しました
投稿日:2025年 08月 19日
8月6日発行の教育学術新聞の2面にあります、
アルカディア学報に、「今こそ職員力の強化を」といタイトルで寄稿しました。
職場等で、お読みになれない方に向けて長いですが、全文を掲載します。
今こそ、職員力の強化を
私学高等教育研究所 客員研究員
合同会社 岩田雅明オフィス代表
岩田 雅明
職員力の重要性
これまで、職員として、短期大学の学長として、大学経営コンサルタントとして、大学に関わってきたが、その中で強く感じていることは、職員力の重要性ということである。コンサルタントとしての活動においても、経営陣と時間をかけて戦略を立案しても、現場がその戦略をきちんと、迅速に実行してくれないと成果にはつながらないわけであるが、多くの大学では、現場が動かないという状況があった。学長として働いていた時にも、お願いしたことがなかなか進まないという状況は、度々あった。職員数が少ないということもあったので、強制しにくい状況もあったが、当然のことながら改善がなかなか進まないということになってしまっていた。
また、情報を共有するという点においても、職員力は重要な要素となる。現場で働く職員が、高校生や受験生、在学生、高校の先生、保護者、就職先企業といった、大学のステークホルダーと接する際に、その人たちが持っている課題やニーズといったことを、少しでもいいから把握しようという意識で接するならば、得られる情報は少なくない。そして、その情報を管理者や経営陣と共有することで、適切な戦略の立案や修正が可能となるからである。
現場の最先端で働いている職員が、最もよく現場の状況を把握することができるので、本来であれば、そこにある程度の権限を委譲し、現場の状況、変化に対応した、適切な対応を取れるようにすることが、効果的、効率的な運営には必要なことになるのであるが、それを可能にするためには、現場で働く職員が、それにふさわしい力量を持っていなければならない。
このようなことから、職員力の高い大学においては、環境の変化に対応した施策を企画し、それを迅速に実行することで、よい結果へとつなげていけるのに対して、そうでない大学においては、環境の変化を感じることもできず、当然ながら、それに対応した施策を企画することもできないという状況になってしまう。その結果、両者の差はますます開いていくということになるのである。
必要とされる力は
では、これから必要とされる職員力といった場合、どのような能力を指すのであろうか。私が、現在、一番必要と感じているのは、主として管理職が対象となるが、マネジメント力である。能力も意欲も高い職員が一人でもいれば、ある程度の状況改善は図れるが、やはりチームで動いたほうが成果は大きくなるので、いかにチームを適切に動かせるかという、リーダーシップも含んだマネジメント力が重要となる。
マネジメント力の重要な要素の一つが、当該部門、チームのゴールを明確に設定するということである。ゴールが明確になると、進むべき方向性が統一されるので、メンバー間の協力体制も整いやすいし、なすべきことも考えやすくなるからである。例えば就職支援部門であれば、夏休みに入る前までに就職内定率を80%以上にするといったように、明確なゴール設定が望ましい。そうすることで、達成度を測ることができるし、進捗状況も把握することができるからである。
二つ目は、管理者とメンバーとの間、そしてメンバー間に良好な人間関係を構築することである。良い関係性が構築されると部門内に対話が生まれることになり、自由な対話の中から課題を解決する道も見出しやすくなる。また考えた施策を実行する際にも、協力し合うことができるので、成果に結びつく確率も高くなるのである。
三つめは、メンバーの意欲を引き出すことである。我が国の現状はどうであろうか。大学の例ではないが、アメリカの調査会社ギャラップ社の従業員エンゲージメント調査(2023年)によれば、組織に貢献しようと熱意をもって働いている人の割合はわずか5%と、世界平均23%、アメリカの31%に比べて極めて低く、世界最低水準となってしまっている。
私もこの数字を見たとき、日本の職場はそれほどひどくはないのではと疑問を感じたのであるが、エンゲージメントの度合いを測る質問の内容を見てみたら、納得したのであった。その質問の多くは、従業員の存在や行動をきちんと上司が承認しているかどうか、そして職場において、個々の従業員の成長が意識され、支援されているかどうかに関するものなのである。したがって、エンケージメントが低いということは、日本の職場においては、従業員に対しての承認の表し方が少ないこと、そして成長を支援する姿勢が弱いということを示すもので、言い換えるならば、管理者のマネジメント力が弱いということになるのである。
職場の上司等が、業務遂行を通じて部下の知識やスキルを向上させる方法をOJT(On-the-Job Training)というが、このマネジメント力をOJTで向上させることは難しいといえる。なぜならば、教える側の上司のマネジメント力が高くないという実態があるからであり、これは大学においても同じ状況と思われるので、OFF-JT(職場外で行う研修)の活用が必要となる。
また、これは管理職研修に限らないが、職場の一人二人が研修で学んでも、職場に戻るとその風土に影響され、元に戻ってしまうということはよく聞く話である。それは非常にもったいないことであるので、そうならないためにも、職場ぐるみの研修、チームで参加する研修といったことを心掛けていただく必要がある。
考える力
もう一つの重要な力は、考える力である。これは、職員全般にとって必要となるものである。今、大学において特に必要とされる考える力は、論理的に考える力である。大学の場合、毎年、同じような業務の繰り返しが多いため、あまり考えなくても業務遂行に支障がないという状況があるように思われる。もちろん、大学を取り巻く環境が良かった時代であれば、特に問題は生じなかったのであるが、現在のように大変厳しく、かつ厳しさが徐々に増していくといった環境下においては、これまでの延長線にはない業務を行っていくことが必要となる。そのために必要とされるのが、論理的に考える力である。
例えば、前述の就職支援部門であれば、人手不足の時代なので、就職させるということでいえば、これまで通りの支援で足りると思われるが、少しでも学生の満足度を高め、大学の評価を上げていくためには、新たな支援を考える必要がある。そのためには、現状、行っている支援等を学生視点に立って点検し、学生の類型ごとに十分かどうかを見極めることである。そうすることで、例えば、すぐに就職活動に取り組めない学生に対する支援が、現状、少し手薄であるといったことに気付けることになり、新しい取り組みを考えられるようになるのである。
これは、現在、多くの大学で最も力を入れている、広報業務においてもしかりである。自学の魅力としてアピールできること、自学の強みは何かということを考え、それを受験生や競合校視点で点検することである。そうすることで、初めてアピールすべき魅力、成果につながるアピールが可能となるのである。そしてそれを一貫性と継続性をもって、ぶれずにアピールすることが大学のブランディングとなるのである。
伝える手法に関しても同様である。目先の派手さなどに惑わされることなく、伝える対象ごとに、効果的な手法を考える必要がある。例えば、駅構内には大学の広告看板が多く掲出されているが、それは誰を対象としたものなのか、対象と想定した人たちに見られ、読まれているのか、掲載されている情報で、その大学の魅力がアピールできているのか、といったことを点検し、修正していく必要がある。
今、女子大や短大に未来はないという雰囲気が強いが、どのような女子大、短大であれば魅力を感じてもらえるのか、どのような学びの領域であれば、それが可能なのかといったことを、論理的に考え対応することで、道は開けてくるのではないだろうか。
職員力の向上が求められる所以である。